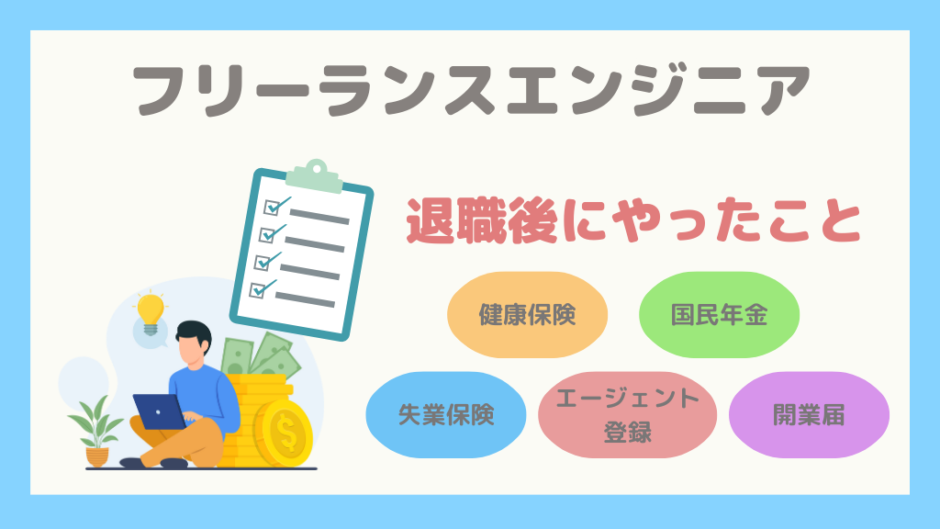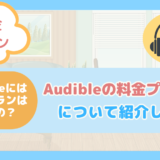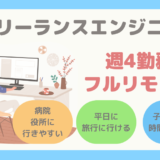会社員として働いている人の中には、別の会社への転職や会社をやめて自営業になることを考えている人もいます。
しかし、一度も退職したことがない場合は、退職前後で何をしたらよいかわからない場合があります。
私は、新卒で入社した会社で9年間働いていましたが、子どもがうまれたことをきっかけにフリーランスエンジニアに転職しました。
本記事では、フリーランスエンジニアへの転職経験をもとに、会社を退職してからフリーランスエンジニアになるまでにやったことを紹介します。
本記事を読むことで、フリーランスエンジニアになるまでの道筋を確認することができます。
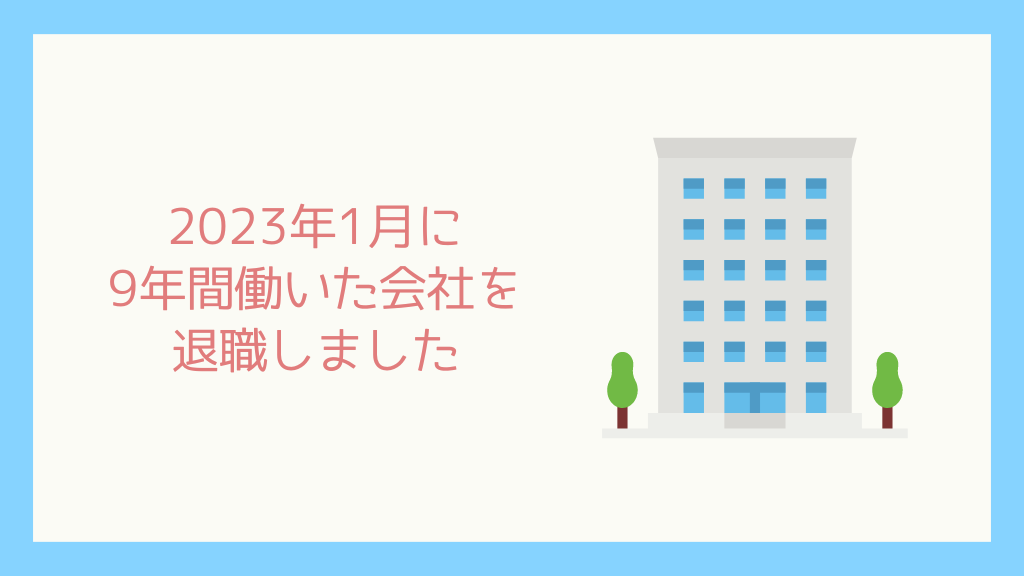
前職は社内システムエンジニア
退職前は、メーカー系のIT子会社で社内システムエンジニアとして働いていました。
主な仕事はシステムの開発と運用で、中堅社員として若手社員の指導も行っていました。
退職のきっかけは、子どもの誕生
システムエンジニアでしたが、退職前はプロジェクトリーダーとして、社内調整や資料作成等がほとんどでした。
プログラミングをすることはほとんどなく、人に指示をしたり、関係者の調整したりという業務ばかりしていました。
「この仕事がほんとうにやりたい仕事なのだろうか?」とモヤモヤしながら働き続けていましたが、子どもがうまれたことをきっかけに将来について考えはじめました。
2023年1月に退職
将来について考えた結果、このまま今の会社で働き続けると後悔すると思い、2023年1月に9年間働いた会社を退職しました。
2023年6月にフリーランスエンジニアとして活動を開始
退職後の数ヶ月は、ハローワークに行ったり、エージェントに登録したりして、転職活動を行っていました。
会社員として転職することも考えましたが、より自由な働き方を求めて、2023年6月にフリーランスエンジニアとして活動を開始しました。
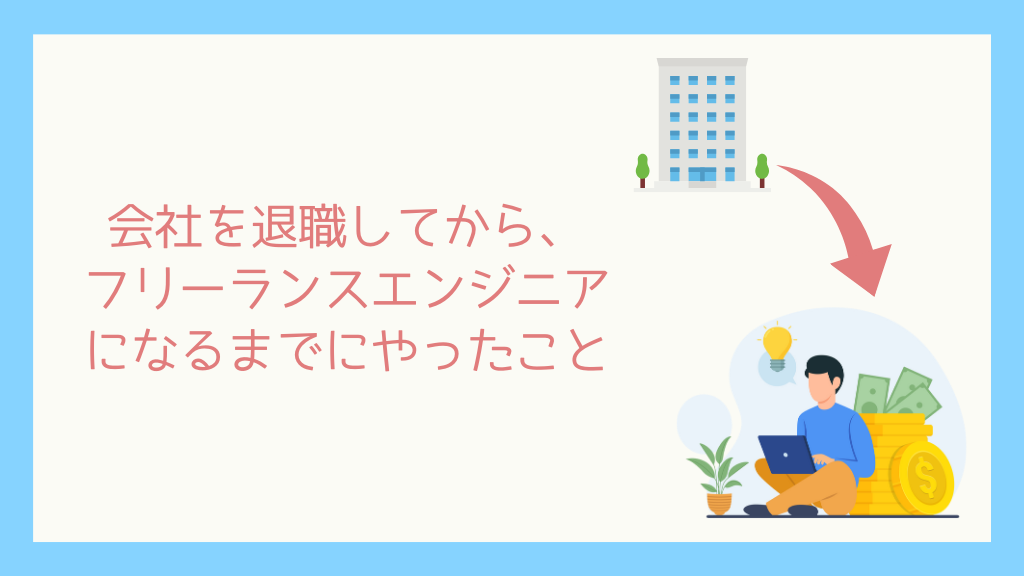
2023年1月に会社を退職してから、2023年6月にフリーランスエンジニアとして活動を開始するまでにやったことを時系列にまとめました。
退職

2023年1月末に、会社を退職しました。
大学卒業してから新卒で勤めたはじめての会社でした。
社会人としての知識をたくさん教えてもらったり、いろんな経験を積ませてもらいました。
ただ、退職前は仕事量が多く、仕事・プライベートともに、あまり余裕がない生活を送っていました。
こどもが生まれたこともあり、働き方や時間の使い方を見直したいと思い、退職することにしました。
健康保険の手続き
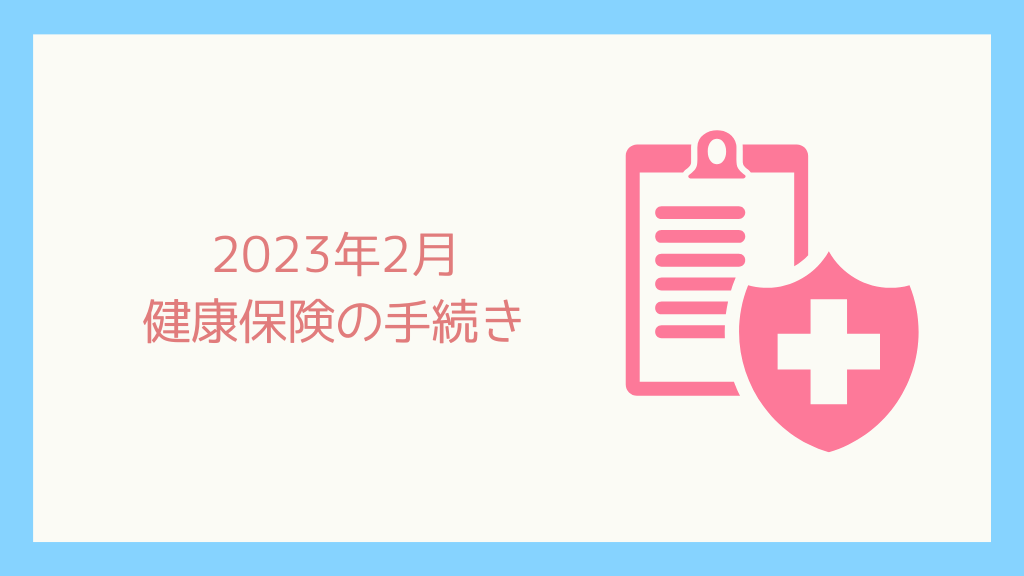
退職後、すぐに行ったのが、「健康保険の手続き」です。
退職後は、退職前の会社の健康保険証が使えなくなってしまいます。
健康保険証がない場合は、病院に行った際に全額負担しないといけません。
また、健康保険の手続きは資格喪失から14日以内に行う必要があるため、早めに手続きを行いました。
健康保険の手続きの選択肢
健康保険の手続きには、2つの選択肢がありました。
- 国民健康保険に加入する
- 会社の健康保険を任意継続する
1つ目の選択肢は、「国民健康保険に加入する」です。
国民健康保険は、会社に勤めていないフリーランスや自営業、無職、年金受給者などを対象とした健康保険です。
会社員でない場合は、国民健康保険に入るのが一般的です。
2つ目の選択肢は、「会社の健康保険を任意継続する」です。
退職した場合、会社の健康保険を継続することができます。
継続が可能な期間は最長2年間で、途中でやめることも可能です。
会社の健康保険の任意継続を選択
比較した結果、会社の健康保険の任意継続の方が保険料が安かったため、会社の健康保険の任意継続を選択しました。
健康保険の手続き方法
会社の健康保険の任意継続を選択したため、前職の健康保険組合の手続き方法に従って手続きしました。
もし、国民健康保険に加入する場合には、居住地の役所で手続きを行うことになります。
国民年金の手続き
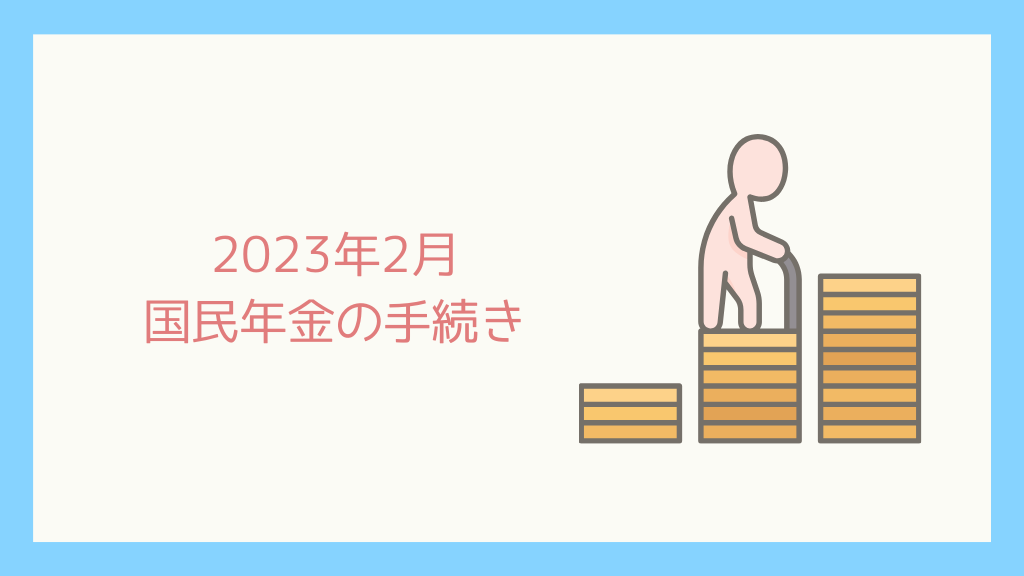
健康保険と同じように、退職した場合に必要なのが「国民年金の手続き」です。
会社員時代は「厚生年金」に加入していましたが、退職後は「国民年金」に加入する必要があります。
国民年金も健康保険と同様に、退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があったため、早めに手続きを行いました。
国民年金の手続き方法
国民年金の手続きは、居住地の役所で行いました。
国民年金の免除申請
退職後すぐに就職しない場合には、国民年金の免除申請ができる場合があります。
免除申請を行うと、保険料が一部、もしくは全額免除されます。
申請者の条件によって、免除可能や免除額が変わってきます。
免除申請の詳細は、居住地の役所で確認することができます。
免除対象期間中は、iDeCoの移管・加入の手続きができなくなるため、iDeCoへの移管等を検討している場合は注意が必要です。
失業保険の手続き
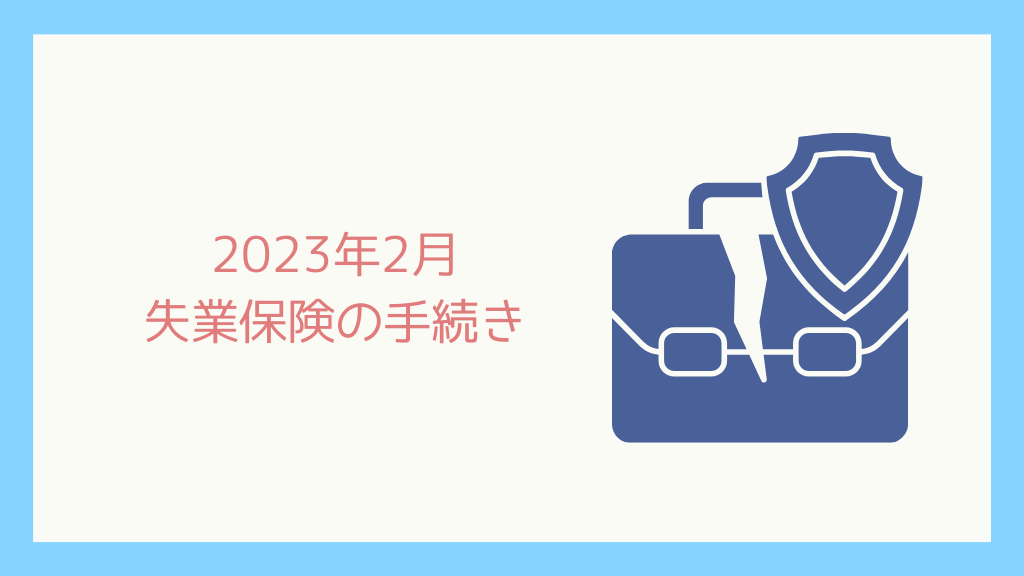
退職後、すぐに再就職するわけではなかったため、「失業保険の手続き」行いました。
失業保険とは
失業保険は、雇用保険の制度の一部で、雇用保険の中の失業手当のことです。
失業保険を申請することで、前職の給料や加入期間に応じて、一定の期間、手当金を受け取ることができます。
失業保険の手続き場所
失業保険の手続きは、最寄りのハローワークで行います。
自分が「雇用保険の対象かどうか」も、ハローワークで確認・相談することができます。
失業保険の手続き
失業保険の手続きを行うためには、「離職票」が必要となります。
離職票は前職の会社から送付されるのですが、受け取りには退職後1〜2週間後くらいかかることがあります。
私の場合は、退職後10日ほど経って自宅に届きました。
失業保険の手続きは、離職票が届いた後、なるべく早めに手続きを行うのがオススメです。
失業保険の注意事項
失業保険は、働く意思や能力があって求職活動をしている人を支援するための手当です。
このため、妊娠や身体の事情等により、すぐに働くことができない場合には、手当を受け取ることはできません。
また、一定期間雇用保険に加入が必要などの細かな条件があるため、自分が雇用保険の対象となるかは事前に確認が必要です。
個人型確定拠出年金の手続き (退職3ヶ月後)
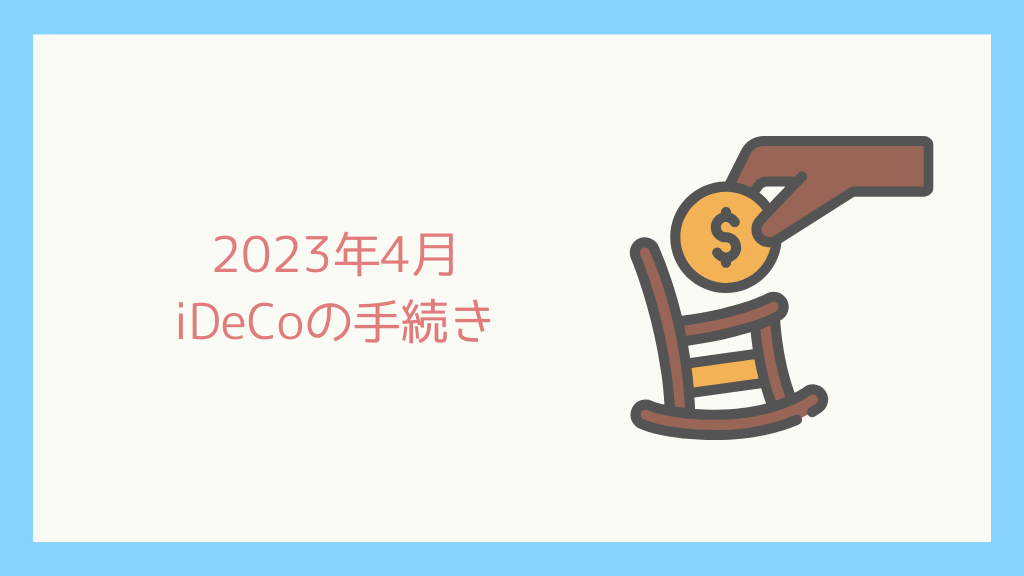
前職の会社で企業型の確定拠出年金に加入していた場合には、「確定拠出年金の手続き」が必要となります。
すぐに再就職し、かつ再就職先にも企業型確定拠出年金があるという場合には、再就職先で手続きすることになりますが、「しばらく失業した状態が続く」、「再就職先に企業型確定拠出年金がない」、「自営業をはじめる」といった場合には、iDeCo(個人型確定拠出年金)に移管が必要となります。
私の場合は、退職時には再就職先が決まっておらず、しばらく失業状態が続いたため、iDeCoへの移管手続きを行いました。
iDeCoへの移管手続き
企業型確定拠出年金からiDeCoへ移管する場合の手順は、次のとおりです。
- iDeCoの移管先を決める
- 退職の1〜2ヶ月後に、「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」が送付される
- 「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」の情報をもとに、IDeCoへの移管・加入申請を行う
iDeCoの場合は、どの会社のiDeCoに移管するかを個人で決めなくてはいけません。
会社ごとに手数料や運用可能な商品が異なります。
私の場合は、NISAでも利用していたSBI証券のiDeCoを利用することにしました。
iDeCoの移管・加入の申請を行うためには、「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」に記載されている情報が必要です。
「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」は、退職の1〜2ヶ月後に送付されるため、それ以降に手続きを行います。
個人型確定拠出年金手続きの注意事項
企業型確定拠出年金から、個人型確定拠出年金へ移管する場合には、次の2点に注意する必要があります。
- iDeCoへの移管は、「資格を喪失した月の翌月から起算して6ヶ月以内」に手続きを完了させる必要がある
- 国民年金の免除期間中は、IDeCoに加入できない
フリーランスエージェントの登録
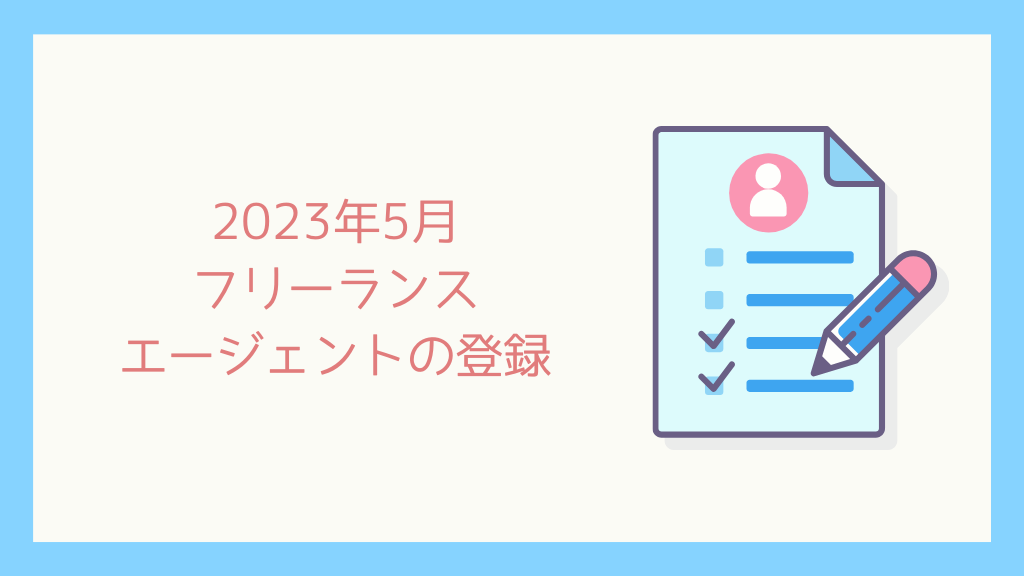
前職では残業時間等も多く、いつも仕事に追われているという感じでした。
こどもが生まれたばかりということもあり、自由に働きたいと考えながら仕事を探していました。
退職後、しばらくはハローワークなどを利用して仕事を探していましたが、退職してから4ヶ月が経ってもう少し範囲を広げて探すために、フリーランスエージェントに登録しました。
オススメのフリーランスエージェント
利用したフリーランスエージェントの中で、オススメのエージェントは次の3つです。
- Midworks
- レバテックフリーランス
- ITPROパートナーズ
オススメのエージェントについては、下記の記事で詳しく紹介しています。
【会社員からの転職】オススメのフリーランスエンジニア向けエージェント3社の紹介
私は、エージェントの中でMidworksを利用して案件を見つけることができました。
Midworksの登録・利用方法は、下記の記事で詳しく紹介しています。
【1週間で仕事が見つかった】フリーランスエンジニア向けエージェントMidworksの登録・利用方法を紹介
フリーランスエンジニアの案件受注
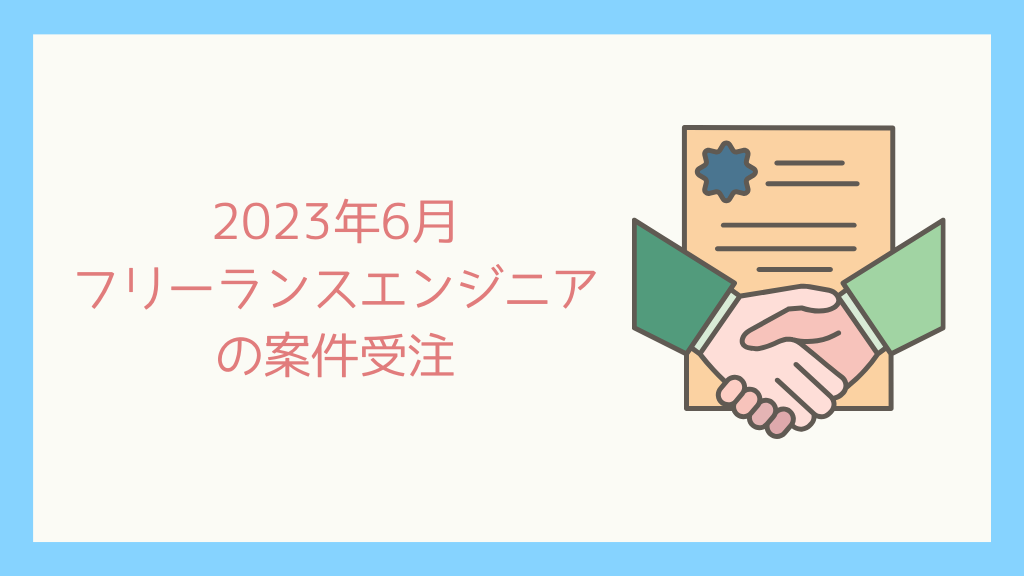
ハローワーク、フリーランスエージェントを使って、週4稼働やフルリモートでできる仕事を探していました。
ハローワークでは、週4稼働やフルリモートの仕事はなかなか見つけることができませんでした。
結果的に、仕事が見つかったのはフリーランスエージェント経由でした。
クライアント企業の方と面談し、6月下旬からフリーランスエンジニアとして案件参画が決まりました。
開業届、青色申告の手続き
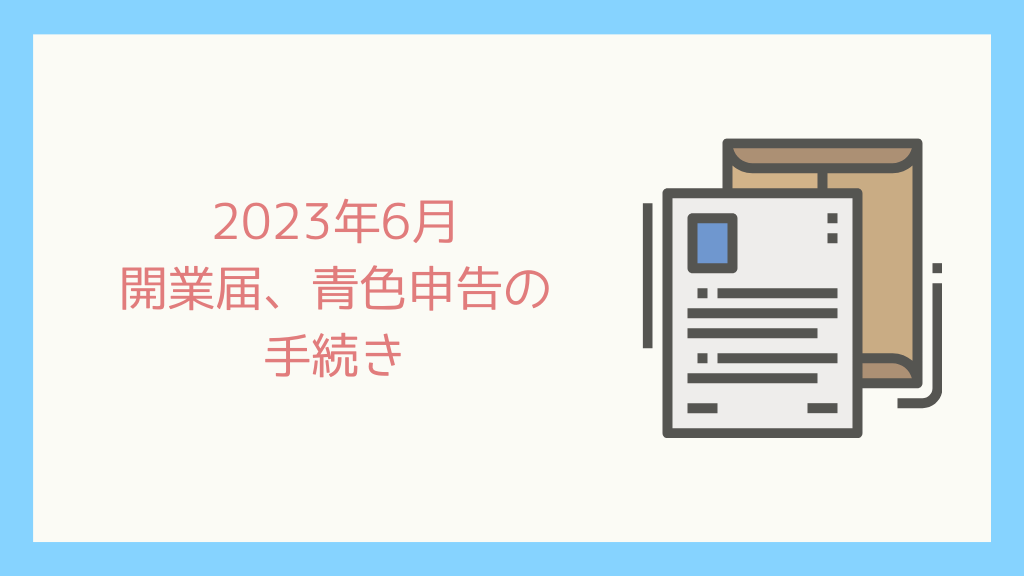
フリーランスエンジニアとして、案件参画が決まったため、開業届と青色申告の手続きを行いました。
開業届
フリーランスエージェントとして仕事をする場合、個人事業主(自営業)となります。
個人で事業をはじめる場合は、開業届を提出する必要があります。
開業届を提出しなくても事業を開始することはできますが、次のようなデメリットがあります。
- 青色申告の控除が受けられない
- 事業用の銀行口座の開設ができない
青色申告、事業向けの銀行口座のどちらも必要だったため、開業届を提出することにしました。
開業届の作り方
開業届の準備をはじめて、「そもそも開業届ってどうやって作るのか?」、「何を書けばよいのか?」がわかりませんでした。
インターネットで開業届の作り方を調べると、無料で使える便利なサービスがあることがわかりました。
開業届を作成するサービスとして、有名なのは「マネーフォワード クラウド開業届」と「freee開業」の2つです。
- マネーフォワード クラウド開業届
- freee開業
私は、家計簿アプリとして「マネーフォワード ME」を利用していたため、「マネーフォワード クラウド開業届」を利用して開業届を作成しました。
マネーフォワード クラウド開業届は、登録フォームにしたがって必要な項目を入力するだけで開業届を作成することができます。また、作成した開業届を印刷してそのまま提出することも可能です。
\ 無料で使える /
/ 登録フォームに必要な項目を入力するだけ \
青色申告
青色申告は、定められた帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。
青色申告を申請して承認されると、最大で65万円の控除を受けることができます。
また、純損失の繰越と繰戻ができるなど、他にもメリットがあります。
青色申告を利用するためには、開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
「青色申告承認申請書」も開業届と同じように、「マネーフォワード クラウド開業届」を利用して作成することができます。
開業届、青色申告の手続き
作成した開業届と青色申告承認申請書」は、最寄りの税務署に提出します。
税務署は、土日はやっていないので、平日の日中に提出が必要です。
ぼくは朝一で提出に行きましたが、5分ほどで手続きが終わりました。
開業届、青色申告の注意事項
開業届は、事業を開始した1ヶ月以内に提出する必要があります。
開業届があることで開業した証明にもなるため、早めに手続きすることがオススメです。
ハローワークでの開業の手続き
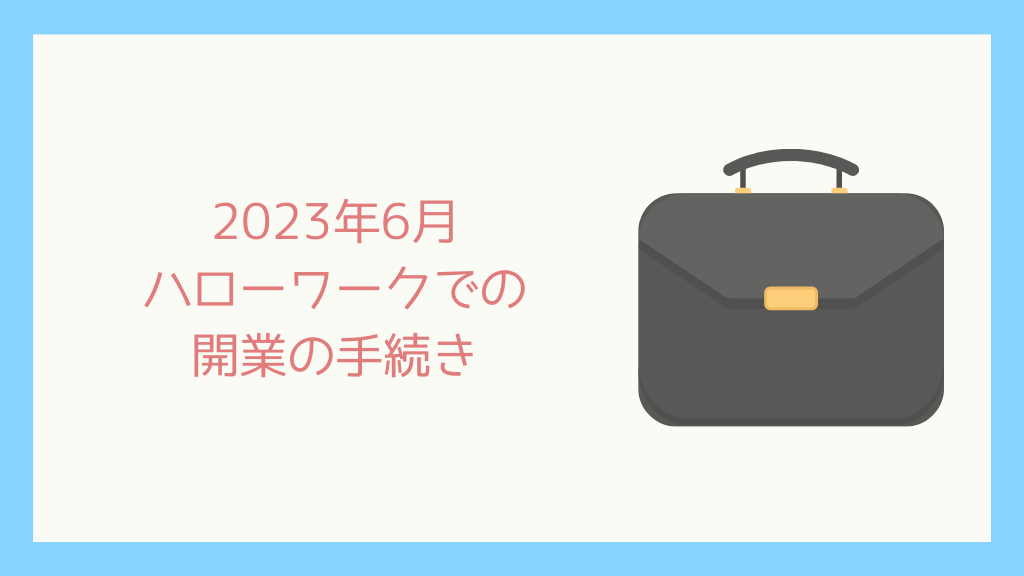
失業保険を受給している場合、開業後はハローワークに開業したことの届出が必要となります。
開業の届出には、「開業日」と「自営を決意した日」の記載が必要になります。
開業日は開業届に記載した日付ですが、自営を決意した日は開業日とは異なる場合があります。
最寄りのハローワークに行って相談したところ、自営を決意した日は「自営業1本で行くと決めた日」との回答でした。
このあたりは、ハローワークによっても回答内容が異なる場合があるので、利用しているハローワークに相談することをオススメします。
事業用の銀行口座の開設
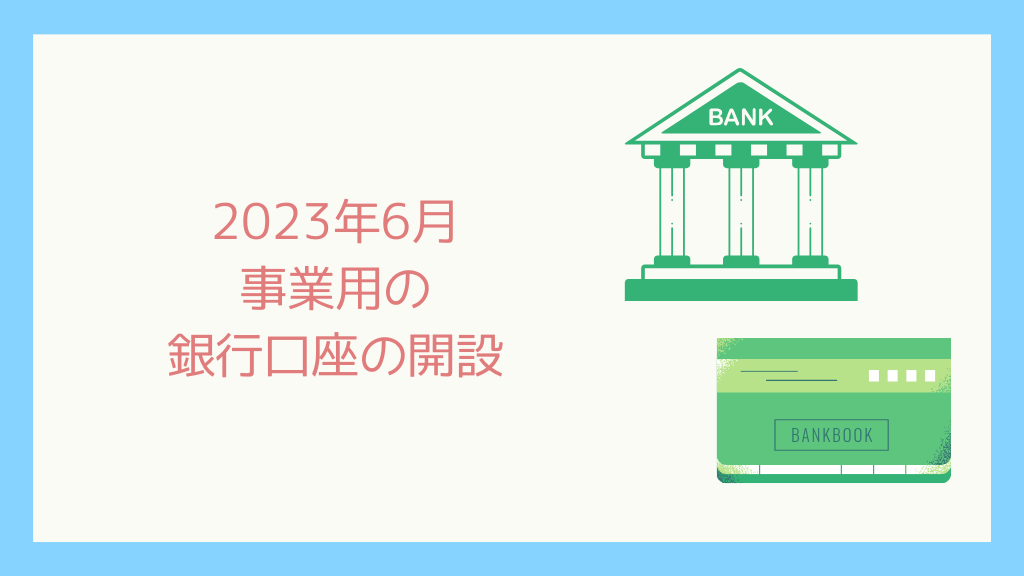
個人で事業を開始するにあたって、事業用の銀行口座を開設しました。
事業用の銀行口座は必須ではありませんが、個人用と事業用で銀行口座をわけておいた方が、確定申告が楽という理由から事業用の銀行口座を開設することにしました。
事業用の銀行口座
事業用の銀行口座は、「GMOあおぞらネット銀行」で開設することにしました。
GMOあおぞらネット銀行は、次のような特徴があります。
- インターネットのみで口座開設が可能
- 個人事業主向けの口座開設が可能
- 屋号付の口座開設が可能 ※屋号のみは不可
GMOあおぞらネット銀行は、窓口に行かずにインターネットのみで口座開設が可能です。
また、個人事業主向けの口座があり、個人事業主でも口座開設がしやすいです。
さらに、屋号付きの口座作成にも対応しており、「氏名 + 屋号」、または「屋号 + 氏名」で口座を開設することができます。 屋号なしで氏名のみでも口座開設が可能です。ただし、屋号のみは不可となっています。
GMOあおぞらネット銀行の個人事業主向け口座の開設手順
GMOあおぞらネット銀行の個人事業主向け口座を開設するためには、個人用の口座開設が必要です。
私の場合は、個人口座もまだ開設していなかったので、個人口座の開設とあわせて次の手順で手続きを行いました。
申請タイミングや時期にもよるかと思いますが、申込から2〜3時間くらいで個人口座の開設が完了しました。
個人事業主向け口座は、申込から1週間ほどで口座を開設できました。
かなりスムーズに個人口座と個人事業主向け口座を開設することができました。
GMOあおぞらネット銀行の個人事業主向け口座の開設の注意事項
個人事業主向け口座の開設の際には、「開業届」と合わせて、「事業内容がわかるホームページのURL、または書類」の提出が必要です。
フリーランスエンジニアの場合は、事業向けのホームページ等がない場合も多いです。
私の場合は、案件受注した際の注文書を提出し、無事に個人事業主向け口座を開設することができました。
ビジネスカードの作成
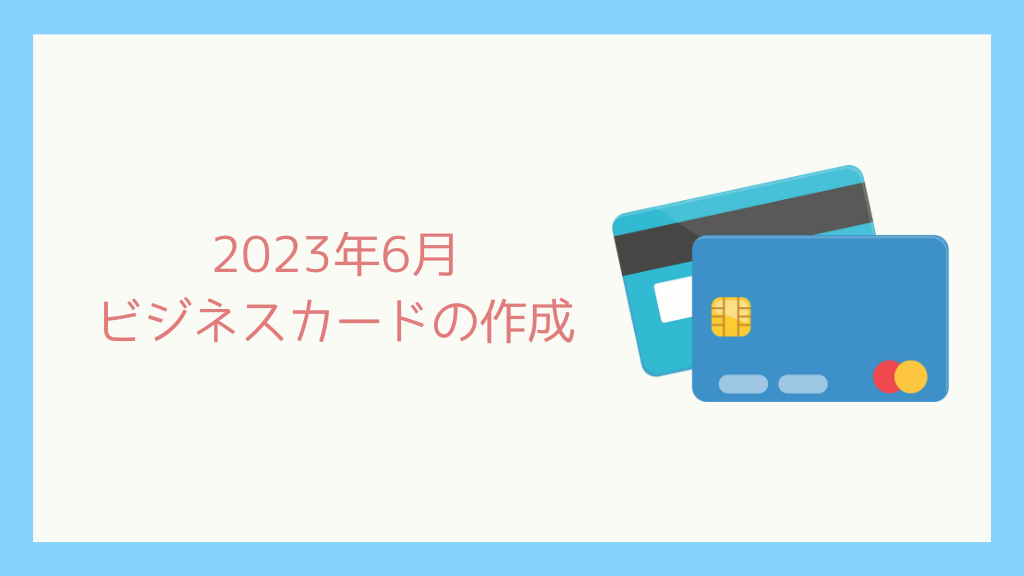
ネットショップで買い物をしたり、サービス利用料を支払ったりするのに、クレジットカードはとても便利です。
しかし、個人事業主(フリーランス)の場合は、審査が必要なクレジットカードを作るのは難しい場合があります。
特に実績のない事業開始直後は、審査が通らないことも多いです。
そんな中で便利なのが、「マネーフォワード ビジネスカード」です。
マネーフォワード ビジネスカード
マネーフォワード ビジネスカードは、審査不要の法人・個人事業主向けカードです。
クレジットカードではなく、事前にお金を入金して利用するプリペイドカードですが、クレジットカードと同じようにネットショップでの買い物やサービス利用料の支払いに使うことができます。
マネーフォワード ビジネスカードの特徴は、大きく次の4つです。
- 審査不要、最短即日発行
プリペイドカードなので、与信審査不要。申込みから最短1週間程度で届く。 - 月の利用上限なし
ウォレットにチャージすれば、上限なしでご利用可能。
※ 1回の決済は最大5,000万円まで - 初期費用・年会費無料 ポイント1〜3%還元
使うほどポイントが貯まり、 貯まったポイントは別の決済にご利用可能。
※リアルカードを複数枚発行される場合は発行手数料、2年目以降ご利用実績がない場合には年会費が発生。
※ 一部ポイント還元できないサービスあり。 - マネーフォワード クラウドとの連携が可能
マネーフォワード クラウドと連携させることで、利用実績を自動で登録。
マネーフォワード ビジネスカードの申し込み
マネーフォワード ビジネスカードは、Webページから申し込みが可能です。
\ 審査不要 /
申し込みから約1週間で、ビジネスカードを受け取ることができました。
マネーフォワード クラウド確定申告とデータ連携もできました。

会計ソフトの利用開始
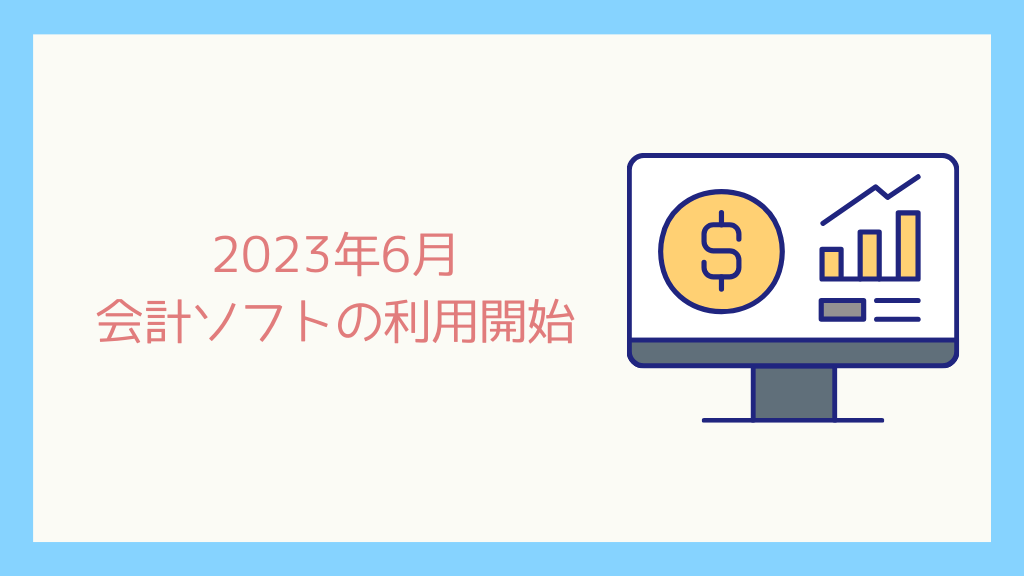
青色申告の控除を受けるためには、「青色申告承認申請書」を事前に提出する以外に、確定申告時に下記の2つの書類を提出する必要があります。
- 青色申告決算書
- 確定申告書
どちらも様式が決まっていますが、はじめてフリーランスとして働く人からすると難しい書類です。
僕自身もこれらの書類を作成したことがありませんでした。
作成が大変だということはわかっていたので、会計ソフトを利用することにしました。
会計ソフト
個人事業主向けの会計ソフトとして有名なのは、次の3つです。
- マネーフォワード クラウド確定申告
- freee
- やよいの青色申告 オンライン
開業届を「マネーフォワードクラウド 開業届」を使って作成したということもあり、「マネーフォワード クラウド確定申告」を利用することにしました。
\ フリーランスの確定申告をかんたんに /
フリーランスエンジニアの活動開始
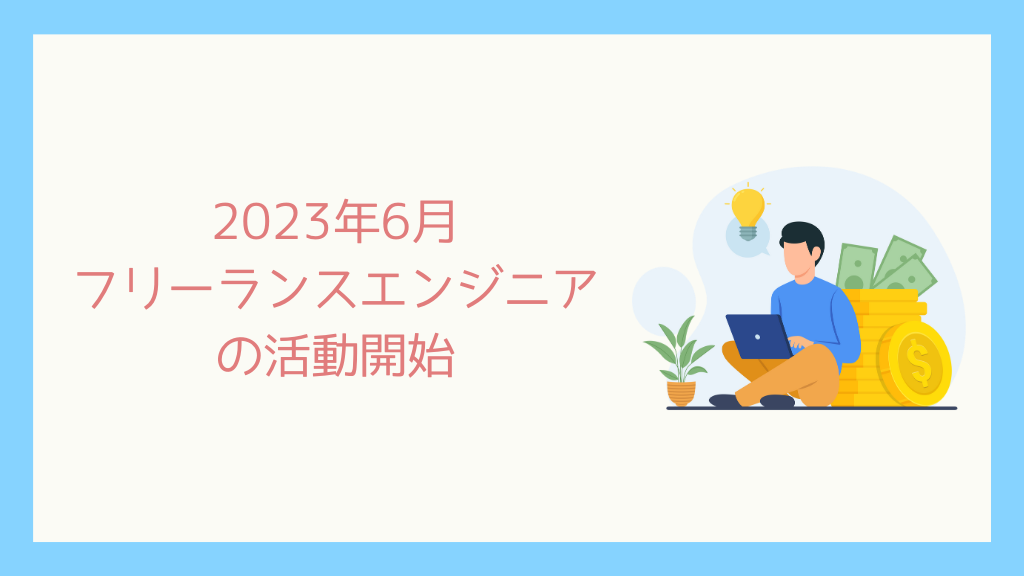
6月下旬から、フリーランスエンジニアとして働きはじめました。
現在は、希望していた働き方に近い働き方ができており、会社員時代よりもストレス少なく過ごせています。
【実例紹介】週4勤務・フルリモートのフリーランスエンジニアの1日の過ごし方
個人事業開始申告書の提出
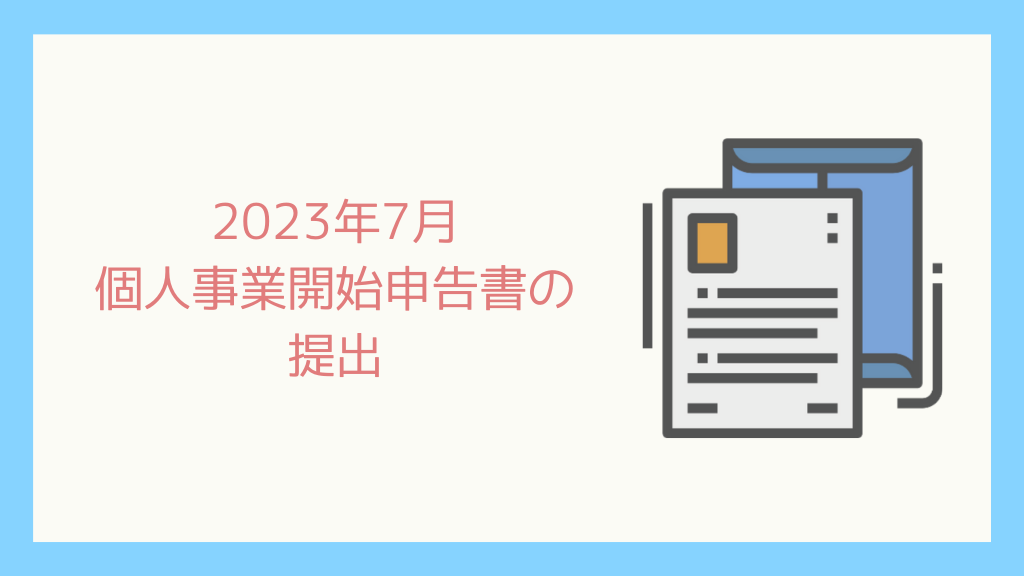
個人で事業を開始した場合、開業届とは別に「個人事業開始申告書の提出」が必要となります。
個人事業開始申告書は、事業をはじめたことを都道府県に報告するために提出するための書類で、個人事業税に関わる書類です。
開業した際に提出が必要な書類なのですが、開業届と異なり提出しない場合のデメリットがないため、提出しない人も多い書類です。
もし提出しなかった場合は、確定申告時に個人事業主の所得の情報は都道府県にも伝わります。
個人事業税の課税対象になった場合には、事業主のところに納税通知書が届くしくみになっています。
個人事業開始申告書の手続き
個人事業開始申告書は、都道府県の税事務所で手続きを行います。
居住地によって、提出先が異なるため、詳細は都道府県のホームページ等で確認が必要となります。
個人事業開始申告書の注意事項
個人事業開始申告書は、都道府県ごとに、提出期限や書類のフォーマットが異なります。
事前に、都道府県のホームページ等で確認することをオススメします。
本記事では、会社を退職してからフリーランスエンジニアになるまでにやったことを紹介しました。
「退職を予定している人」、「フリーランスに興味がある人」、「今の働き方に不満があって、何か変えたいと思っている人」の参考になればうれしいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以上、「【体験談】会社を退職してから、フリーランスエンジニアになるまでにやったことまとめ」でした。